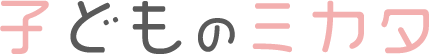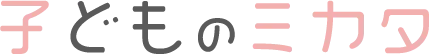『もう無理!』から大逆転!科学でわかる、子どもの挑戦を支える声かけの力
2025/02/02
「子どもが『もう無理!』と言ったとき、あなたはどう声をかけていますか?
『こうすればできるよ!』と教えることもあれば、『頑張りなさい!』と励ますこともあるでしょう。
でも、どれだけ工夫して声をかけても、うまくいかないと感じたことはありませんか?」
前回、4歳の女の子がコーンアイスのおもちゃを高く積み上げる遊びに挑戦している場面をご紹介しました。彼女は最高記録の10個を積み上げたものの、それ以上は難しく、『もう無理!』と諦めかけていました。
そのとき、私は『そっと置いてみたらどうかな?』と声をかけました。
この一言が、彼女の目つきを変え、最終的に14個を積み上げる挑戦を成功させたのです。」
一般的な声かけが子どもの脳にどのような影響を与えるか、脳科学の視点で見てみましょう。
よくある声かけの例
• 「こうすればできるよ!」
• 「頑張りなさい!」
• 「そんなこと言ってるからできないんだよ!」
脳科学的な影響
1. 前頭前皮質が十分に活性化されない
• 解決策を提示されると、子どもが「どうすればいいか」を自分で考える余地が奪われます。このとき、前頭前皮質(考える力や計画を司る部分)が十分に働かず、自主性や集中力が育ちにくくなります。
2. ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌
• 強い励ましや指摘は、子どもにプレッシャーを与え、脳内でストレスホルモンが分泌されます。
これにより、集中力が低下し、挑戦を避ける傾向が生まれる場合があります。
3. ドーパミンの分泌が不足
• 指示通りに動くだけでは「自分でやった」という達成感が得られず、脳内でドーパミン(やる気や喜びを引き出す物質)の分泌が促進されにくくなります。
4. 今回のアプローチを脳科学視点で振り返る
一方で、『そっと置いてみたらどうかな?』という声かけは、脳科学的に以下のようなメリットがありました。
1. 前頭前皮質を刺激し、自主性を促進
この一言は、具体的な答えを与えるのではなく、子ども自身が「どうすればうまくいくか」を考える余地を提供します。
これにより、前頭前皮質が活性化し、問題解決能力や集中力が高まります。
2. 心理的安全性を確保し、ストレスを軽減
「惜しいね」「あと少しだったね」という声かけは、結果ではなく努力を評価するものですこれにより、子どもが安心して挑戦を続けられる環境が生まれ、コルチゾールの分泌が抑えられます。
3. ドーパミンの分泌を促進
子どもが自分で考えた方法で成功すると、脳の報酬系が刺激され、ドーパミンが分泌されますこれにより、「もっとやってみたい」という気持ちが引き出され、挑戦意欲が高まります。
5. 第一回のエピソードと科学的根拠を結びつける
「彼女は、最初は『無理!』と諦めかけていましたが、自分で考える余地を与えられることで、次第に『どうすれば積み上げられるか』に集中し始めました。
このとき、前頭前皮質が働き、挑戦に必要な計画力が引き出されたのです。
また、挑戦を認める声かけが心理的安全性を高めたことで、ストレスを感じることなく挑戦を続け、最終的に14個のアイスを積み上げる成功体験を得ました。
----------------------------------------------------------------------
子どものミカタ
代表: 井阪 有希
〒596-0825
大阪府岸和田市土生町
電話番号 : 090-5901-6133
教育方針のお悩みはオンラインで
----------------------------------------------------------------------
幼稚園教諭5年・保育士20年目
才能クリエイト協会上級コーチ
株式会社マインズ 社員コーチング
コーチング実績は2,000人を超え、現在は、実践練習ができるワークショップも主催
子育てのストレスを科学的に理解するマンガを制作中!